キルケゴールは実存主義の哲学者です。実存主義は「自分ってなんだろう?」「こういうふうに生きたい」という思い、本来の自分を求めるあり方をいいます。
キリスト教がこう言っているから…先生がこう言っているから…と受動的に考えるばかりでなく、自分はこうありたい、自分の存在はこうあるべきだというところまで踏みこみます。
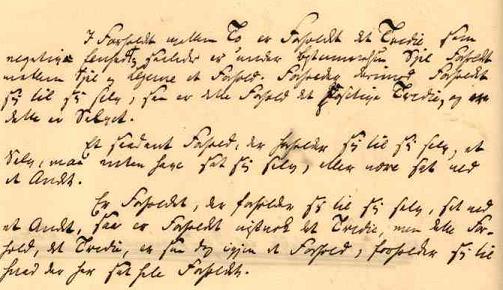
センター試験の高校倫理は著作物に関する問題がよく出ます。キルケゴールの主著は『死に至る病』と『あれか、これか』。
主体的真理と例外者
キルケゴールは主体的真理を重視しました。主体的真理とは、自分にとって重要な真実です。自分は他人でない自分という存在だと自覚するには、この主体的真理が必要になる。
キルケゴールがこのように考えた背景は、自分が「例外者」であるという自覚によるかもしれない[2]。自分は他人や社会と異なるという「例外者」の感覚が、主体的真理を求める姿勢につながったとも考えられます。
キルケゴールの実存主義
キルケゴールはキリスト教から出発します。裏切り、貧困、病気といった絶望の果てに、人はたった一人になる。助けてくれる者はいない。そうした状況で頼れるものは何か?
キルケゴールはそれを神だと考えました。究極の絶望で人は「単独者」になります[1]。単独者という言葉は重要キーワードです。単独者になると、人は神と一対一になり、神にすがるようになる。
この状態こそ、人の究極的な実存、つまり本来の自分。神と一対一になるまでの自分は、いくつかの実存を通ります。
美的実存
倫理的実存
宗教的実存
最初は美的実存で、この状態にある時、人は快楽を追求します。楽しいことを求めますが、やがて自分を見失っていく。これが美的実存の限界です。
次に倫理的実存になります。この状態でようやく人は倫理的に行動できるようになる。快楽に浸っているだけの人生から、倫理的な人生を送るようになる。しかしそれも限界があり、やがて神という超越者にすがるようになる。
神と一対一になった状態がキルケゴールの重視する宗教的実存です。
ニーチェとの違い
キルケゴールとニーチェの違いはキリスト教を肯定するか、否定するかという点です。
- キルケゴール … キリスト教を肯定
- ニーチェ … キリスト教を否定
キルケゴールは弱い自分を救うためにキリスト教を求めます。最初から弱いという前提に立つのです。
しかしニーチェはキリスト教を、弱者のための思想とバッサリ否定する。ニーチェは弱さを克服して、力を求めるところに本来の人間性があると考えました。
キリスト教を軸にして、キルケゴールとニーチェは同じ実存主義という概念を真反対の立場から考えたといえます。
チェック
参考文献
- 高等学校新倫理、平成29年、清水書院、118
- 高等学校新倫理、平成29年、清水書院、117








