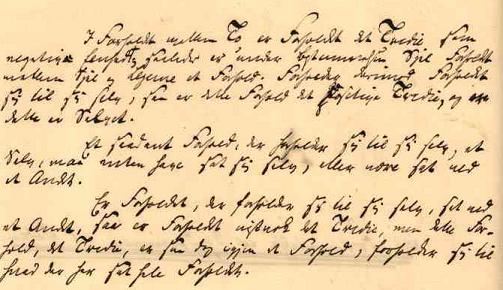グレゴリウス11世(在位1370年〜1378年)は、カトリック教会史の転換点に立つ重要な教皇です。彼はアヴィニョン教皇庁における最後の教皇であり、その死後には西方教会の大分裂(西方シスマ)が始まることになりました。
アヴィニョン教皇庁の終焉
13世紀から続いた「教皇のバビロン捕囚」と呼ばれる時代、教皇庁はフランスのアヴィニョンに置かれ、フランス王権の強い影響を受けていました。イタリアの諸都市や聖職者たちはこの状況に不満を募らせ、ローマに教皇を戻すべきだとの声が高まっていました。
ローマ帰還を決断した背景
フランス王国への依存による批判
聖カタリナの説得と影響
聖カタリナの役割
シエナの聖カタリナは手紙や直接の説得を通じてグレゴリウス11世にローマ帰還を促しました。彼女の情熱的な呼びかけは大きな影響を与え、1377年、ついに教皇はローマへ戻る決断を下しました。これによって一応「バビロン捕囚」は終わりを告げました。
西方シスマへの道
しかし、グレゴリウス11世が1378年に死去すると、後継の教皇選出をめぐって深刻な対立が生じます。ローマで選ばれた教皇とアヴィニョンに擁立された教皇が並立し、教会は分裂状態に陥りました。これが約40年間続く西方シスマの始まりでした。
歴史的意義
グレゴリウス11世のローマ帰還は、中世後期の教会史における大きな転換点でした。それは教皇庁の権威回復を意図したものでしたが、皮肉にも彼の死後に教会分裂の引き金となり、教会の権威をさらに揺るがす結果を招きました。彼の治世は、教皇権の行方をめぐる中世末期ヨーロッパの緊張を象徴する出来事として記憶されています。