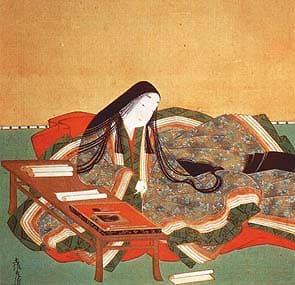枕草子第百三十段「九月ばかり」の原文を文法と単語に注意して読みましょう。
枕草子「九月ばかり」
九月ばかり、夜一夜降りあかしつる雨の、今朝はやみて、朝日いとけざやかにさし出でたるに、前栽の露、こぼるばかりぬれかかりたるも、いとをかし。
透垣の羅文、軒の上にかいたる蜘蛛の巣のこぼれ殘りたるに、雨のかかりたるが白き玉をつらぬきたるやうなるこそ、いみじうあはれにをかしけれ。
すこし日たけぬれば、萩などのいとおもげなるに、露の落つるに枝のうち動きて、人も手ふれぬに、ふとかみざまへあがりたるも、いみじうをかしといひたることどもの、人の心にはつゆをかしからじと思ふこそまたをかしけれ。
解説
九月ばかり、夜一夜降りあかしつる雨の、今朝はやみて、朝日いとけざやかにさし出でたるに
現代語訳
九月頃、一晩中降って夜を明かした雨が、今朝はやんで、朝日がとてもきわだって出てくると
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| ばかり | 頃 |
| 夜一夜 | 一晩中 |
| けざやかなり | きわだっている |
「けざやかなり」の「け」が「あ」になると「あざやかなり」という現代語になります。「今朝はやみて」は「今朝は」「やみて」です。
前栽の露、こぼるばかりぬれかかりたるも、いとをかし。
現代語訳
庭の草の露がこぼれるほどぬれているのも、とても趣深い。
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| 前栽 | 庭の草 |
| いと | とても |
| をかし | 趣深い |
透垣の羅文、軒の上にかいたる蜘蛛の巣のこぼれ殘りたるに
現代語訳
透垣の羅文や軒の上にわたっている蜘蛛の巣がくずれたように殘っているところに
雨のかかりたるが白き玉をつらぬきたるやうなるこそ、いみじうあはれにをかしけれ。
現代語訳
雨が降りかかっているようすが、白い玉を(糸で)通しているような感じで、とても風情があっておもしろい。
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| いみじう | 「いみじく」の音便形 |
| いみじ | なみなみでない すばらしい ひどい |
| あはれなり | 風情がある |
この文は典型的な係り結びの法則の文です。「つらぬきたるやうなるこそ」の「こそ」は係助詞の「こそ」で文末は已然形で終わらせるため、最後の「をかしけれ」が已然形となっています。
すこし日たけぬれば、萩などのいとおもげなるに、露の落つるに枝のうち動きて、人も手ふれぬに、ふとかみざまへあがりたるも
現代語訳
少し日が高くなってくると、萩などがずっしり重そうであるのに、露が落ちると枝が動いて、誰の手も触れていないのに、ふと上のほうにあがっていくのも
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| たけ | 「たく」の連用形 |
| たく | (日が)高くなる |
| おもげなり | 重そうである |
| かみざま | 上のほう |
「日たけぬれば」は次のように品詞分解します。
日たけぬれば
=日(名詞)
+たけ(動詞・カ行下二段「たく」連用形)
+ぬれ(助動詞・完了「ぬ」已然形)
+ば(接続助詞)
「荻などのいとおもげなるに」の「の」は「が」という意味。「おもげなり」は形容動詞のように見えますが、もともとは形容詞「おもし」です。
古文では「げ」は形容詞の語幹について形容動詞化する働きがあります。「げ」がつくと「~のような」と表現の強さがぼかされます。
おもし(形容詞)
→おも(形容詞の語幹)
→おも+げ
→おもげ
→おもげなり(形容動詞)
いみじうをかしといひたることどもの、人の心にはつゆをかしからじと思ふこそまたをかしけれ。
現代語訳
とてもおもしろいということなどが、他の人の心にはまったくおもしろくないだろうと思われるのもまた、おもしろい。
「つゆ」は非常に重要な単語で、下に打消の言葉をともなって「まったく~ない」という構文を作ります。ここでは「じ」がその打消言葉に相当しています。
さらに「こそ」という係助詞は係り結びの法則によって文末の「をかし」を已然形「をかしけれ」にしています。